運動感覚
私たち人間は「自分がどんな動きをしているか」を視覚に頼ることなくその運動を通した身体感覚でもって認識することができます。
この「どんな運動がどのくらい行われているか」を自らに知らせてくれる情報を運動感覚と呼びます。
この感覚は、視覚以外の種々の感覚に運動にまつわる感覚が意味づけされた結果となります。
簡単に言えば、脳内で運動イメージが作られるというようなものです。
これがあるおかげで目を瞑ったままでも自分の動きが分かるのです。
運動感覚は痛みと関連している
運動感覚は基本的に普段は認識されるものではありません。
これは自転車の乗り方を言葉で説明するのが難しいように、運動感覚は主観的、一人称であり意識に上りにくいからだと言われています。
運動に伴う痛み
しかし、身体部位に何かしらの障害が起きて、動きに伴う痛みが発生したとき、その動きと痛みは強く認識され、運動感覚と痛みの結びつきが強くなります。
つまり、脳内で痛み=動きという意味づけが起こり、これが運動のイメージとなって記憶されます。
痛みと動きが結びつく
このイメージは、いったん作られると障害や外傷そのものが改善されても脳に強く残ります。
つまり、痛みは運動感覚を通して学習されるものでもあるということです。
運動感覚と運動イメージ
実際に肌で感じる運動感覚は、脳内の運動イメージと深く関わっていると知られています。
運動イメージとは実際の運動を行わずとも運動が起こっているような感覚を想起できること、すなわち運動感覚を想起することをいいます。
運動をイメージしているときに活性化する脳の部位が実際の運動を行っているときとほとんど共通していることから、運動をイメージは運動のリハーサルのようなものであると推測されています。
これらのことから、疾患や障害が回復しているはずにも関わらず痛みが起こるのは、運動イメージの中に痛みが内包されている可能性があるということが考えられます。
実際に治癒後、目立った原因がないにも関わらず痛みを訴え続ける人は運動イメージのなかに痛みを想起してしまう人もいるようです。
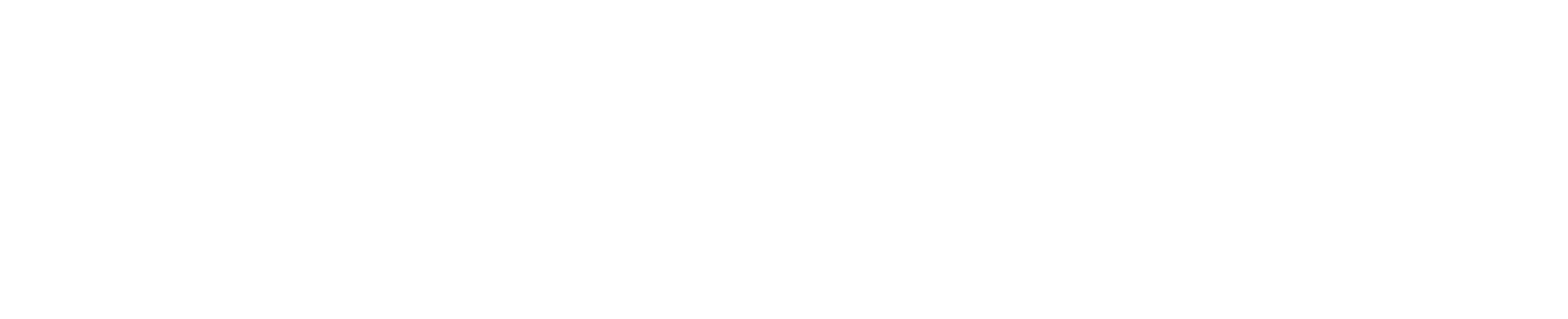



コメント