天気が悪くなると体がダルくなったり、古傷が痛んだり、頭痛が起きたり……。
誰もが悩むこの現象には、酸素濃度、耳の中のセンサー、ヒスタミンが関わっているとされています。
気圧と自律神経
人間の約70%は水分で出来ています。
そのため「圧」の影響を強く受け、わずか0.1気圧の変化にも敏感に反応します。
頭痛やだるさは低気圧が続いたり気圧が変動したことの反動といえます。
これは主に自律神経のバランスが乱れることが原因で、酸素濃度や内耳による気圧感知が関係しています。
低気圧と酸素濃度
通常、晴れた日は高気圧なため、地表付近の酸素濃度が比較的多め。
ところが雨天のような低気圧では、相対的に地表付近の酸素濃度が低下しています。
酸素濃度の低下は、副交感神経が優位に働き、身体の活動性を低下させるトリガーとなるのです。
その結果現れるのが頭痛、脱力感やだるさ、眠気です。
また低気圧では身体の種々の組織が膨張し、それによる血行不良や痛み、だるさなどが引き起こされることも。
内耳による気圧感知
我々の耳の奥には、内耳という平衡覚を司る器官がありますが、近年の研究によると気圧の変化を感知するセンサーも備えていることが分かりました。
内耳は脳と接続しており、気圧変化を脳に伝えますが、これが同時に身体へのストレス反応にもなってしまいます。
人間はストレス反応が起こると交感神経が優位になり、これにより血管収縮が生じ、頭痛や慢性痛症状が現れてしまうのです。
ヒスタミン
低気圧環境に長く晒されると、ヒスタミンという物質が過剰に分泌されます。
このヒスタミンは血管拡張作用があるため、血管膨張による神経の圧迫を引き起こしてしまいます。
これが低気圧時に起こる痛みと関連しているようです。
対処法・改善法
気象病の原因となる気候自体をコントロールすることはできませんが、自律神経バランスを整えることや血流の改善を図ることが対処法として重要です。
副交感神経が優位な状態では安静にしたりストレッチしたりお風呂に入ったり、交感神経が優位な状態ではストレッチの他、軽いゆっくりとした運動も効果的です。
加えて日頃から栄養・休養に気をつけて適度な運動を行うことが大切です。
参考
Lowering barometric pressure induces neuronal activation in the superior vestibular nucleus in mice
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0211297
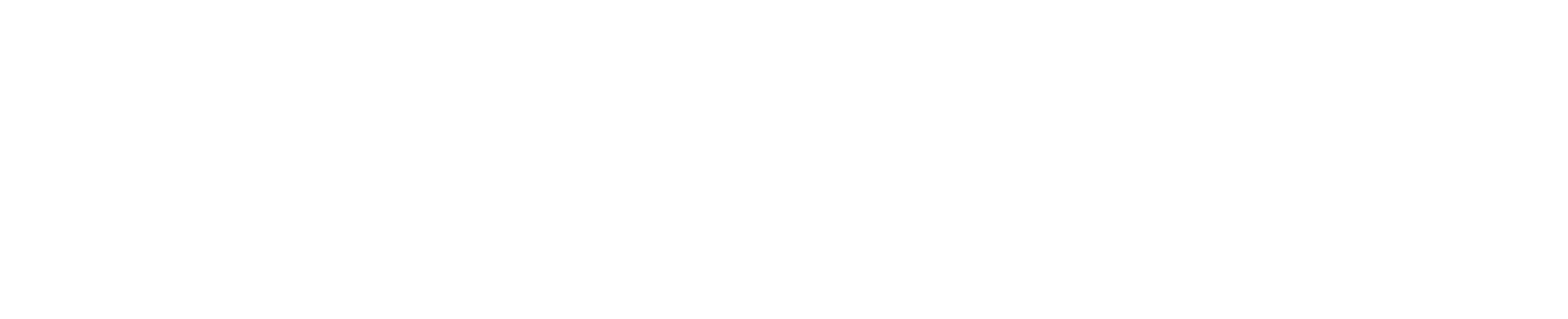



コメント